電子
物体は電子を取り込むことで負に帯電し、電子を失った物体は正に帯電する。また、導線の内部を電子が移動することで、電流が流れる。このように電磁気学でたびたび登場した電子だが、いったいどのようにして発見され、研究が進められてきたのだろうか。
電子の発見

雲が帯電し、地上との間に数億Vの電圧が生じると、空気中を電流が流れる。このように、気体の中を電流が流れる現象を気体放電という。

続いて気体を封入した容器を用意し、その両端に高電圧をかける気体放電の実験を考えよう。この気体の圧力を1atm(≒105Pa)から徐々に下げていくと、103Pa付近で、気体の種類ごとに特有の光を発するようになる。例えば、ネオンNeはオレンジ、アルゴンArは青紫、キセノンXeは水色に光る。これを真空放電という。
しかし、さらに容器内の気体の圧力を下げていくと、1Pa付近で、気体の種類によらず薄緑色の蛍光を発するようになる。発見当時、この薄緑色の線は陰極側から飛び出しているように見えることから、陰極線とよばれた。その後、陰極線は電場や磁場によって曲げられる等の実験結果から、陰極線の正体が負の電荷をもつ粒子であることが分かり、この粒子は電子と呼ばれるようになった。
J.J.トムソンの実験(比電荷の測定)
電子はとても小さく、直接目で見ることはできない。では、電子の電気量eや質量mなどの物理量はどのようにして測定すればよいのだろうか。

1897年,J.J.トムソンは図のような実験で電子の電荷eと質量mの比e/mを求めた。これを比電荷という。
上下に設置した極板に向けて、電子を速さvで投射する。極板を通過する間に極板から電子が受ける静電気力は、

であるから、運動方程式より、


のように、y方向の加速度aを求めることができる。ここで、極板の長さをlとすると、電子が極板を通過する時間t_1は、x方向の速度vが変化しないことから、

と分かる。ゆえに、極板を通過する瞬間の電子のy方向の速度v_yは、等加速度直線運動の式から
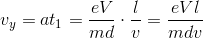
と求まる。さらに、電子が極板を通過する間のy方向のずれy_1も、等加速度直線運動の式から

と求まる。
さて、極板から飛び出した電子は斜め向きに等速直線運動を行い、蛍光面へと到達する。蛍光面が光ることで、電子が飛んできた方向が分かるというわけだ。ここで、極板を飛び出してから蛍光面へ到達するまでの時間t_2を求めると、

であるから、電子が蛍光面に到達する点の、蛍光面の中心からのずれyは、

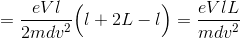
と計算することができる。この式から、比電荷

が計算できそうに思えるが、よく考えると1つ問題がある。それは、電子の速さvが分からないこと。vの値をどうにか測定する必要があるのだ。

そこで、電子が極板を通過する間に、電場Eとは別に磁束密度Bの電場を与える。すると、電子は電場Eから受ける静電気力Fとは別に、磁場からローレンツ力

を受けることになる。そして、この磁束密度Bがある値のとき、電子は直進する。このとき、電子が受ける静電気力Fとローレンツ力fはつり合っていると考えられるから、

式が成り立ち、

電子の元の速さvを求めることができるわけだ。最後に、この値を用いることで、

比電荷が計算できるのだ。この式へ、実際に測定したVやyやBなどの数値を入れて計算すると、

という結果が得られる。
ミリカンの実験(電気素量の測定)

ミリカンは1909~1916年の間、帯電させた油滴の観察によって電気素量eを求めることに成功した。
質量Mの油滴を滴下させると、落下の速さvに比例する抵抗力kvがはがらき、やがて重力Mgとつり合う。

油滴が電気量qに帯電している場合、鉛直上向きに電場Eをかけると、電場の強さによって油滴は上昇を始める。すると、今度は鉛直下向きに空気抵抗kvがはたらき、やがて力がつり合う。

この2式より、空中を漂っていて直接測定することが困難な油滴の質量Mを消去することができる。

よって、油滴の電気量qが、

と測定できる。
この電気量qは、空気のイオンが油滴に付着するごとに変化し、その速度vも変化する。ミリカンはこの実験を繰り返し行うことで、電気量が、

という最小単位を持つことを発見した。これを電気素量といい、電子は-eの電気量を持つ。
J.J.トムソンによる比電荷e/mと、ミリカンによる電気素量eの測定により、電子の質量m

も分かる。
